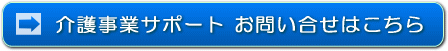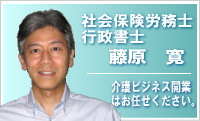実務経験ナシの開業・運営方法
Q デイサービスの実務経験が無い、又は、会社を経営したことが無い
といった場合、どうやって開業・運営すればいいのでしょうか?
A 実際にデイサービスで働いてみてノウハウを学ぶことがベストだと思いますが、何らかの理由でその方法が取れない場合は、次の4つの方法が考えられます。
(1)フランチャイズに加盟する
(2)実務経験者を雇い入れる
(3)書籍、ブログ等を見て運営方法を学ぶ
(4)開業、運営のプロに業務を委託する
上記選択肢の中からのいずれかひとつ、又は、複数を組み合わせながら開業・運営することになります。
ではまず、(1)の「フランチャイズに加盟する」ですが・・・
皆様もご存知の通り、フランチャイズのメリットは、
まったくの未経験者でも容易に事業をはじめることができることです。
フランチャイズ本部から開業・運営に関する情報の提供、指導及びアドバイアス等がありますので、安心して開業・運営することができます。
フランチャイズへの加盟により、開業のハードルが下がり成功への道が開かれたように感じます。
でも、よく考えてみてください。
確かに、実務経験が無いと最初は不安で誰かにすがり付きたくなる気持ちはよくわかります。
でも、それは最初だけです。
半年も運営すれば、その後は自立してやっていけます。
この半年だけのために、高額な加盟金と5~8%のロイヤリティを払うのですか?
私がお金を出すわけではありませんので、そこは自由に選択してくださって結構ですが、私ならフランチャイズはNOです。
では、どうやって開業・運営すればいいのでしょうか?
上記(2)(3)(4)をバランスよく組み合わせて開業・運営しましょう。
(2)実務経験者を雇い入れる
デイサービスは小規模でしたら最低3名、通常規模だと4名のスタッフの配置が必要です。
詳しくは 人員基準 をご覧ください。
あなたが介護スタッフとして現場で働く場合であっても、最低2名は雇わなければいけません。そして多くの場合、有資格の『生活相談員』を雇うことになります。
であれば、『生活相談員』はデイサービス実務の経験者を雇いましょう。
生活相談員は、デイサービス運営の中心になる方です。妥協は禁物です。
なるべく実務経験豊富な方を採用し、運営のノウハウを吸収しましょう。
ただし、今現場では介護スタッフが不足しています。(地域にもよりますが)
特に優秀な方を採用するのが難しくなっています。
ですから、募集は早めに行いましょう。
(3)書籍、ブログ等を見て運営方法を学ぶ
経営者はあなたです。
優秀なスタッフを採用したとしても、
あなた自身に運営の知識が無いと効果は半減してしまいます。
そこで、あなた自身も運営方法を勉強しましょう。
ここでは書籍をご紹介いたします。
この本は、生活相談員の業務について書かれた本ですが、
デイサービスの運営に必要な手続きがズラリと載っています。
実務経験の無い新米の経営者にとっては、運営のヒントになるようなことも載っています。
ただし、ページ数の制限上、細かい部分は省略されていますので、更なる知識を得るには別の書籍が必要になるでしょう。が、入門書としてはお勧めできるものです。一度ご購読くださいませ。
必要な知識を習得して、生活相談員と協力しながら運営しましょう。
当ページの最後にこの本の内容を簡単に紹介していますので、
購入の参考にしてください。
(4)開業、運営のプロに委託する
ややこしい、と感じる手続きは外部に委託しましょう。
弊事務所の紹介となってしまい恐縮ですが、
「ややこしい」と感じる手続きは、専門家に委託しましょう。
いわゆる「ややこしい」手続きは次のものです。
①会社設立(定款作成)
②デイサービスの指定申請
③経理の記帳、税務申告
④給与計算、スタッフの労働保険、社会保険、雇用の手続き
⑤介護報酬の請求
①・②は開業前、③~⑤は開業後の手続きです。
これらの手続きは、直接的に利益を生み出しません。
自分でやるのではなく専門家に任せて、空いた時間でサービスなり営業なりを頑張ってください。その方がずっと利益が上がります。
では具体的に誰に委託(相談)すればよいのか?
①会社設立(定款作成)
行政書士、司法書士
会社を設立する際は、行政書士又は司法書士にご相談ください。
②デイサービス指定申請の代行
社会保険労務士
指定申請の書類作成・申請の代行は、
「社会保険労務士」の資格が無いと出来ません。
当然フランチャイズ本部が代行することは出来ませんので、
加盟した場合でも自分で書類を作成して、申請しなければなりません。
③経理の記帳、税務申告
公認会計士または税理士など
複雑な手続きですから、依頼することになると思います。
④給与計算、スタッフの労働保険、社会保険、雇用の手続き
社会保険労務士など
労働法に違反した場合、指定を取り消される場合があります。
不安を感じたら、労働法の専門家である社会保険労務士にご依頼ください。スタッフの給与計算、雇用管理をサポート致します。
⑤介護報酬の請求
多くの場合、介護報酬請求ソフトを利用します。
請求手続きは、委託ではなく事業所で行う必要があります。
(請求方法は、ソフトを提供する会社から説明を受けることになります。)
書籍のご紹介
デイサービス生活相談員 業務必携
簡単ではございますが、本の紹介をさせていただきます。
興味がある方はご購読くださいませ。少し高いですがその価値はあると思います。
注意1 初版を基に紹介しております。改訂版は内容が多少異なっているようですので、その点ご了承くださいませ。
注意2 入門書です。実務経験のある方は物足りなさを感じるかもしれません。
大きく次の5つの項目について解説されています。
1.生活相談員とは何なのか?
2.生活相談員に求められる役割とは何なのか?
3.新規利用者獲得のために、生活相談員は何をすべきか?
4.生活相談員の業務の手順は?
(これはデイサービス運営の手順に繋がります。)
5.生活相談員の業務事例集
特に重要なのは
3.新規利用者獲得のための業務
4.生活相談員の業務手順
5.生活相談員の業務事例
の3点です。
ここでは、この3点に絞ってご紹介致します。
3.新規利用者獲得のための業務について
新規に利用者を獲得するために何をすればよいか?
についての解説です。
ページ数は限られていますが、利用者獲得のための心構え・アプローチの方法などが載っており、読んでいて「なるほど」と思うことが結構あります。
4.生活相談員の業務手順
生活相談員の業務手順ですが、管理者(経営者)なら当然知っておかなければならない内容だと思います。
具体的には、次の流れで解説されています。
(一部内容は省略しています。)
(1)利用契約
①ケアマネージャーから利用者受け入れの連絡
②利用者状況の確認
③契約日の日程調整
④利用者宅に訪問(契約)
⑤利用開始
(2)通所介護計画書の作成
①アセスメントにより利用者の現状を把握し、
生活する上での課題を抽出する
②ケアマネージャーからケアプランを受け取る
③通所介護計画書の原案を作成
④利用者宅に訪問し原案の説明
⑤署名・捺印
(3)モニタリングの実施
モニタリングとは・・・その現状を把握して、通所介護計画の目標の
進捗と評価、課題の抽出をすること
①日々記録を取る
②定期的なモニタリング(現状把握と見直し)
③モニタリング項目・内容の確認
④ケアマネージャーへの報告
(4)サービス担当者会議について
サービス担当者会議とは・・・ケアプランを作成する際に、サービス関係者が集まり内容を検討する会議のこと
(5)サービス提供票について
サービス提供票とは・・・ケアプランに基づいてサービスを実施するための利用者の1カ月の予定表のこと
(6)給付管理について
介護報酬費の請求の手順について
(7)行事の企画・運営について
(8)送迎について
送迎のルート確認や職員の配置、送迎記録と利用者の状況把握など
5.生活相談員の業務事例
生活相談員の業務についての事例が載っています。
ここでは、
・利用者と介護者の間をどのようにつなぐか
・現場と家族の間をどのようにつなぐか
・利用者とケアマネージャーをどのようにつなぐか
・利用者の生活全体の中から援助の課題を見つけ、
いかにチームで共有するか
・制度的にも手に余る事例をどのように機関につなぐか
といった視点から事例を展開されています。
経験に基づいたストーリーです。
実際に自分がこのような状況に立たされたときに どのように対応すればよいかなど、シュミレーションを行いましょう。
お問い合わせ
兵庫県・大阪府内でのデイサービスの開業・運営はお任せください。
お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士・社会保険労務士事務所
TEL:078-707-3366
電話受付 平日 9:00~18:00